2008年に亡くなったジェフリー・ラタは、私の最も好きなマジシャンというか、クリエイターの一人です。
彼の作品は、リチャード・カウフマン著「COINMAGIC」や「Richard’s Almanac」、それから2冊の彼のレクチャーノートを初めとして、いくつかの文献に散らばっていますが、そう数は多くないと思います。
今回ご紹介の”From the Elfin Hoard”は、彼の作品の中でも最も好きなもののひとつで、Stephen Minch著「Spectacle」に掲載されています。
この本は元々、New York Magic Symposium Collectionの一冊として出される予定の内容だったそうで、シンポジウムコレクションと同じくクロースアップ、メンタリズム、ステージ等バラエティに富んだ内容です。
リサ・メナ、ジェイ・サンキー、トミー・ワンダーやデビッド・ロスなど、日本で開催の第5回シンポジウムと共通するメンバーによる作品もあります。
このコレクションで、ジェフ・ラタによる作品は2つ。ひとつはカードで、もうひとつがコイン、今回ご紹介の”From the Elfin Hoard”です。
Elfin Hoardとは聞きなれない言葉ですが、”Elfin”は「妖精の」、”Hoard”は「(財宝の)蔵」みたいな意味のようです。
訳するならば、「妖精の宝物庫の中から」みたいな感じでしょうか。メルヘンチックな名前ですね。
この作品に関しては、10年ほど前に旧サイトでも簡単に取り上げています。よろしければ併せてごらんください。
ジェフ・ラタの”From the Elfin Hoard”
では、動画をアップしてありますので、よろしければご覧ください。
現象は単純で、3枚のコインが1枚ずつ消えて、また1枚ずつ現れる、というものです。
消失と出現、コインマジックでは非常にメジャーなテーマですが、シンプルなだけに奥が深いプロットでもあります。
消失と出現を扱った手順としては、当サイトで今までに紹介したものでは、デビッド・ロスによるⅣやハンギング・コインなどがあります。
これらの手順にはそれぞれ独自の狙いがありますが、この”From the Elfin Hoard”の狙いは、おそらく1枚目の消失と改めの鮮やかさでしょう。
この作品には、とある一般的なギミックコインを用いていますが、その使い方が独創的で、他に類を見ないものです。
使うタイミングが通常とは異なっています。
一般的な手順では、消失の前にこのギミックを使用しますが、この手順では消失の後での使用となっています。
このタイミングの”ずれ”が、とくに多少の知識あるマジシャンにとっては意表を付くものでしょう。
全体の枚数が3枚であるというのも、上記の原理を最大限に生かす構成です。
リチャード・カウフマンは、著書「COINMAGIC」の中でジェフ・ラタの”CopsilBrass”について、”Masterpiece of Construction”(構成の傑作)と呼んでいます。
手順の各要素が分かちがたく結びつき補完し合う、原理を最大限に生かす構成。これこそがジェフ・ラタの作品の最大の魅力だと思っています。
この”From the Elfin Hoard”は小品手順ですが、これも間違いなく”Masterpiece of Construction”のひとつと呼べるでしょう。
ジェフ・ラタの”From the Elfin Hoard”をネタにして色々・・・
バリエーションの紹介というか、自分でこんなのを考えてみました、という話です。
この作品が解説された「Spectacle」には、ジェフ・ラタ自身によるバリエーションとして、パースフレームを併用した手順もある、と書かれていました。
またさらに、筆者個人の意見と断りつつ、パースフレームの併用は手順のシンプルさを殺すのであまり好きではない、ような記述もあります。
原案より良くないとは言われても、やっぱり気になる記述です。
ここから色々とアイデアを膨らませて、自分なりにこの手順にパースフレームを取り入れた手順を組み立てたりもしていました。
ジェフ・ラタの来日レクチャー時に、私は少人数限定のプライベートレクチャーにも参加したので、その後の飲み会で色々と見せ合う機会がありました。その席で私なりのやり方を演じたところ、ラタ氏も彼のパースフレーム手順を見せてくれました。
しかしそのときはメモも取っておらず、さらにもう10年近くの月日が流れ、ラタ氏の手順がどんなものであったのか思い出せません。少なくとも私が考えた手順よりはずっと巧妙だと感じた記憶はあるのですが。
この手順以外にも、1コインのスローモーション・バニッシュなど、文献に発表されたことがない手順も色々と教えていただいたのですが、やっぱり年月を経ると記憶は薄れますね。
上でリンクした旧サイトの記事では、近々ジェフ・ラタ作品集が刊行予定との内容が書かれています。
これは、MagicCafeという掲示板サイトでジェフ・ラタ自身に教えてもらったことで、あの時点では企画はあったのだと思うのですが、その後この話はまったく聞かないですね。立ち消えになってしまったのかも知れません。ラタ氏の逝去も、急逝といっても良い突然なものでしたから。
閑話休題。
今回またこの手順を色々といじっていて、現在の自分なりの、”From the Elfin Hoard”のパースフレーム版を考えてみました。
これは、以前考案した手順とは異なり、今回新しく組み立ててみたものです。
少なくとも、ラタ氏にお見せした手順よりは洗練度が上がっていると、自分なりには思っていますが、いかがでしょうか。
原案の構成は、まず普通に3枚のコインがある状態から始めて、「消失」→「出現」という流れとなっています。
しかしパースフレームを取り入れるとなると、やっぱりフレームからの出現現象から入りたいところです。しかし、出現から入って、原案そのままの流れだと、「出現」→「消失」→「出現」となって据わりが悪い感じです。
やっぱり、冒頭がパースフレームだけの状態から始まるのならば、最後もパースフレームだけの状態で終わりたい。
というような思考で、この動画のような手順になっています。
この手順の最後の箇所は、六人部慶彦氏のシリンダー・アンド・コインの技法を参考にさせていただきました。
この六人部氏の技法については、ジェフ・ラタ氏も”Nowhere Palm”という名称で類似の見せ方を使用しています。
このあたりの連想も影響したかも知れません。
ジェフ・ラタの”From the Elfin Hoard”を解説した文献等
この作品は、Stephan Minch著「Spectacles」に解説されています。
パースフレームを使用した手順については、奇妙な小銭入れなどもご覧ください。今回の動画手順にも一部の動きを取り入れています。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。





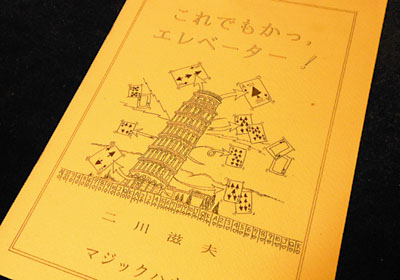


この記事へのコメントはありません。