「カードマジック事典」のアンビシャスカードの項目の最初の作品として、ダイ・バーノンの手順が掲載されています。皆さんはこれを演じられたことがあるでしょうか?
私はありませんでした。
現在はYoutubeに夥しい数のマジック動画が上がっており、そこそこ有名な手品の中でアップされていないものを探すほうが難しいぐらいですが、このダイ・バーノンのアンビシャスカードは見当たりません。私の周囲でも演じている人は見たことがありませんし、プロマジシャンの方でもこの手順は難しいと聞いたこともあります。
アンビシャスカードというプロット自体は現在でも(むしろ現在は、かも)非常にメジャーで、プロアマ問わず大抵のマジシャンが演じています。それにもかかわらず、バーノン手順を演じる人があまり居ないのはなぜなのか。
当サイトでは「カードマジック事典動画」というカテゴリを設けて、以前からゆっくりとしたペースではありますが映像化を続けています。
今回はこのダイ・バーノンのアンビシャスカードを、私の技量の及ぶ範囲ではありますが映像化して、この手順の意味や難しさについて考えてみようと思います。
ダイ・バーノンのアンビシャスカード
アンビシャスカードのプロット自体は19世紀ごろからあったようですが、このテーマがカードマジックの中でも主要なプロットとしての市民権を得たのは、このバーノン手順が発表されてからのことであるようです。
このバーノンのアンビシャスカードは1961年刊行の書籍「Stars of Magic」に掲載されましたが、この本に載っているいくつかのバーノン作品は、使用されている技法や方法論の面でエポックメイキングと見なされているものがあります。
カッティング・ジ・エーセスはダブルカットを紹介したことで有名ですが、同様にこのアンビシャスカードは、DL(省略して頭文字のみ)とアンビシャスカードを誰にでも使いやすい形で組み合わせて見せたところに意義があったのではないでしょうか。
では、動画をアップしてありますので、よろしければご覧ください。
まずお断りしておきたいのは、「カードマジック事典」および原典の「Stars of Magic」の解説では、何度かダブルカットを用いることを指示されている箇所があります。しかしそれらの部分についてはバーノン本人は実際にはパスを用いていたようで、上の動画ではそれに拠った形としています。
生身の観客相手に演じたわけではなく、カメラの前で撮影しただけですが、やっぱりこれはなかなかに難しい手順だと感じます。
まず手順全体について思うことは、パスやトップチェンジといった直截的な技法が、現代よく演じられているアンビシャスカードに比べるならば多目であるということです。
パスやトップチェンジ、あるいはパームといった直截的な技法は言わば原始的で、バーノン以前の古い時代には主流の技法であったと思われます。そういった過去から現代に亘るカードマジックの流れは、基本的にはそういった原始的な手法を、もっとストレスの少ないやり方に代替していったという面があります。
バーノンのアンビシャスカードにしても、おそらくはそれ以前のやり方に比べれば現代的に直されたものであったはずですが、現代のアンビシャスカードに比べれば少し古典的と思えるのは、仕方のないところでしょうか。
現代的な感覚でこの手順を構成するならば、パス(元解説ではダブルカット)を用いる箇所の全部もしくはいくつかは、ティルトを用いるのが普通でしょうね。この手順が発表された頃は、まだティルトは一般的な技法ではありませんでした。ティルトももちろん万能ではありえませんが、少なくとも古典的な方法に比べれば、説得力があるだけでなく、手数をいくつもショートカットできる便利な方法でもあります。
ティルトと同様の概念の技法を、バーノンがこの頃から使用していた可能性はありますが、エド・マーローによるティルトが一般に発表されたのは1962年のことで、バーノンのアンビシャスカードよりも後のことです。ティルトは一般にはマーローの技法とされていますが、同時期にバーノンもDepth Illusionとして同様の技法を考案していました。
この手順については一箇所、ちょっと私にとって解釈に迷うところがあります。
それは、観客の意表をついてトップではなくボトムからカードが出てくる直前の部分です。
ここでは、カードをすり替えたのではないかと疑わせるような動作をした後、カードの表を見せて安心させるわけですが、そこからデックの下半分を半ばパームするような動作でトップに持ってきます。
ここの部分を、マジシャンとしてはどう見せたいのか、個人的に判断に迷うところがあります。
「Stars of Magic」の解説では、「これで観客はトップに持ってきたと思うだろう」と書かれているだけで、どういう理由でそう思うのか、どういう意図があるのかについての説明がありません。個人的な感覚では、この動きを無垢な目で見るだけでは、カードが上に上がってきたと疑わせる説得力が、それほどあるようには思えないのです。
ここの解釈(マジシャンがどう見せたいのかの意図)について、2通りが考えられると思っています。
ひとつ目は、いわゆるプッシュ・イン・チェンジを模倣するという表現です。アンビシャスカードの手順において、明らかに異なるカードを見せて疑わせた後で、実際にはすり替えていないとか、あるいはその逆の見せ方など、フェイントムーブによく使われる技法です。
マジシャン的な目線でバーノン手順のこの箇所を見れば、観客のカードを見せた後、プッシュ・イン・チェンジによってトップにコントロールした、という表現にも見えます。
ただ、プッシュ・イン・チェンジをわざと疑わせるというのは、一般観客が相手ではちょっと考えにくい気がします。この手順が発表された「Stars of Magic」はどちらかというと一般学習者あるいは中級以前の人向けのテキストですから、そこまでMagician Foolerな要素が盛り込まれているというのもなんだか似つかわしくないようにも思えます。それともこの時代、プッシュ・イン・チェンジは現在よりもよく知られた一般的な技法であったということでしょうか。
上記に加えて、素直にプッシュ・イン・チェンジを模倣するならば、デックの下半分はヒンズー・シャッフル式にトップに回せば問題ないとも思います。しかしバーノンのアンビシャスカードでは、あえて不器用なパームのような見せ方をすることとなっています。
このあたりも、プッシュ・イン・チェンジの模倣として解釈して良いのかどうか迷うところです。
もうひとつの解釈としては、いわゆるサイドスチール的な動きによって、差し込まれたカードをトップに持ってきたという見せ方です。
これであれば、不器用なパームに見せかけるというのも納得がゆくことですし、カードを直接抜き取ってトップに置くという操作も、一般の観客が想像しそうなことですから、フェイント的な模倣としてはありえそうに思います。
私自身の個人的な解釈としては、上記のうち後者の見せ方のほうが有力だと、以前から考えていました。
ただ最近、「Vernon Revelation」のDVDで晩年のバーノン本人による実演を観たところ、少なくとも本人の意図はスチールではないように思えました。
そういう経緯で、上の私の動画では、どちらかというと前者のプッシュ・イン・チェンジ模倣に近いニュアンスでやってみたつもりです。まあちょっと、迷いながらですが^^;
ダイ・バーノンのアンビシャスカードの、演出の難しさ
上の節で述べたことはすべて、この手順の技術的な側面です。
それ以外にバーノンのアンビシャスカードが難しいと個人的に思う大きな理由として、演出・見せ方の難しさがあります。
それは、ほぼ全編に亘って観客をわざと疑わせて引っ掛けるようなムーブが連続する点です。
まず3回目の現象での偽トップチェンジ、それから上述のプッシュ・イン・チェンジに似たムーブ、さらにあからさまなグライドの模倣など。
以前にバーノンのカップ・アンド・ボールの記事でも書いたことですが、バーノン作品には意外と、この種の心理的フックを仕掛ける場面が頻発します。専門家を騙す目的の手順ではもちろんですが、比較的一般向けと思える手順でもそうです。
そういった中でも、クラシックとして広く知られた作品の中では、このバーノンのアンビシャスカードは、その種のフェイントムーブが一番多い作品ではないでしょうか。
「Stars of Magic」に掲載した以上、バーノン自身はこの作品を専門家を引っ掛ける手順として提供したわけではないと思います。
この手順に組み込まれた企みはつまり「怪しいぞ」「今のは分かった」と思わせた瞬間にその裏をかく、その連続です。これを意図通りにしっかりとコントロールして表現し、企み通りに観客が翻弄されれば、これは確かに最高のエンターテイメントになるでしょう。ことさらにマジックを演じなくても、客いじりだけでも巧ければ芸になるのですから。
しかしこれは難しい。難しすぎる。
これを演じて観客を満足させられるようなマジシャンになってみたい、という意味で、目指すべき頂を仰ぎ見る気分です。
同じ技法でも、ニュアンスを変えて演じ分けるあたりがとくに難しい。
シークレットムーブとしてのトップチェンジを実行した直後に、フェイクのトップチェンジを演じて観客に疑わせるところなど。
ただし、難しさとその価値を認めつつも、やっぱり個人的にはちょっと時代に合わない部分も無いではないと思います。
上で述べた、現代ならばティルトを用いる云々という点もそうですが、フェイクムーブで引っ掛けるパターンも、ちょっと現代には合わなくなったと思えるところがあります。
例えばグライドは、古くは非常にありふれた、素人でも知っているような技法だったのでしょう。だからこの手順のような表現が心理的フックとなりえるわけですが、現代ではグライドがそこまで認知されているかどうか、疑問があります。
プッシュ・イン・チェンジの模倣なのかどうなのか迷うと、上で述べた部分も、そういった時代的な背景がないと、本当には理解しにくいのかもしれません。
まあその分、時代的な落差をも克服するぐらいの高い表現力で、しっかりと演じれば、現代でも十分通用するのでしょうけどね。
こういったところも、この手順の難しさです。
ダイ・バーノンのアンビシャスカードを解説した文献等
この手順は1961年の「Stars of Magic」に掲載されました。この本は名著としてマジック史に燦然と輝く文献で、かつて大阪のRRMCによって日本語訳されたこともありますが、この日本語版は当初から限定発行であり、今からの入手は難しいと思います。英語版なら比較的入手は容易です。
日本語では、「カードマジック事典」に掲載があります。この本にはアンビシャスカードが2手順掲載されており、そのうちのアンビシャスカード①というのがこのバーノン作品です。
また、映像資料としては、「ヴァーノン・リベレーションズ」の1巻に、バーノン本人による演技が収録されています。
高齢のため手元のおぼつかない演技ではありますが、師本人が手順を実演しながら、マイケル・アマー、スティーブ・フリーマン、ゲリー・ウォレットの3人相手に語っている映像は貴重なものです。






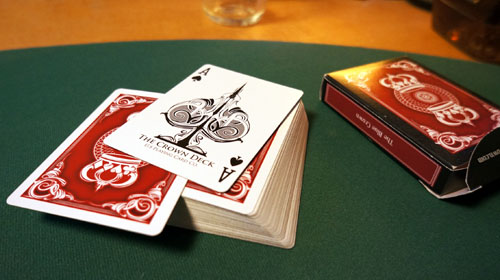



この記事へのコメントはありません。