1組のトランプではなく、数枚程度の少ない枚数のカードで演じるカードマジックを、パケット・トリックと言います。パケット・トリックは現代ではとくに隆盛を極めており、リセットやオイル・アンド・ウォーターといった、レギュラーカードで演じるものから、ワイルドカードなどのようにレギュラー以外の構成で演じるものまで、夥しいほどの作品数があります。
その中でも、4枚のカードだけを使って演じるパケット・トリックは意外に少ないのです。
今回ご紹介するドクター・デイリーのラストトリックは、4枚のエースだけを使うマジックの中でも、ダイ・バーノンのツイスティング・ジ・エーセスと並んで最も有名なものの一つです。
なお、以前にもドクター・デイリーの作品として、“Motile”というコインマジックを取り上げました。この時点ではドクター・ダレーという表記をしていました。
しかし、この表記はどちらかと言えば、英語スペルをそのままカタカナ読みした表記です。原語の発音は「デイリー」に近く聞こえます。また、高木重朗先生を始めとして何人かの奇術家の方も「デイリー」の表記を採っておられます。
以上のようなことを勘案して、当サイトでも今後はドクター・デイリーの表記を採ることとします。
(Motileの記事のほうも訂正しました)
ドクター・デイリーのラストトリック
ドクター・ジェイコブ・デイリー”Dr. Jacob Daley”はアマチュアマジシャンで、ドクターの敬称が示すとおり、本業は外科医です。しかしただのアマチュアではなく、ダイ・バーノンをはじめとして当代の一流マジシャンの多くと親交がありました。本人も、名著スターズ・オブ・マジックに作品が取り上げられたほどの名人です。
ラストトリックというのは、彼が死の直前に発表したトリックで、文字通り遺作となったことから呼び習わされた名称です。
彼の死については、あるパーティーに招かれて奇術を演じた直後、体調を崩して倒れこみ、そのまま帰らぬ人となったということが知られています。ただ、ラストトリックというのはこの最期のショーで演じたトリックというわけではなく、その数日前に奇術家の会合で発表したトリックということのようです。
このあたりの経緯については、高名な奇術研究家である石田隆信氏のコラムに詳しいです。
石田氏のコラムでは、上記の経緯だけでなく、現在の著名マジシャンによって演じられている各種ハンドリングと、原案の相違点も詳細に述べられています。またさらに遡って、ドクター・デイリー以前のこのテーマに類する情報まで報告されています。
本当は読者の方に対しては、ドクター・デイリーのラストトリックのことをお知りになりたければ、石田氏のコラムをお読みください、で済みそうな気もしています。
しかしまあ当サイトとしては、これまでネット上にない新たな情報を提供するのが目的というわけではありません。どちらかと言えば、自分が得た知識や経験を文章や動画の形でアウトプットし、逆に自分自身の血肉とすることのほうが第一目的です。また、サイト継続という形で、自分自身の学びのモチベーションを保つという意味もあります。自分本位ですみません^^;
そういうわけで、今回自分の言葉で改めてこの作品を紹介することにも、一定の意味はあるだろうと思う次第です。
前置きが長くなりましたが、動画をアップしてありますので、よろしければご覧ください。
非常にシンプルな現象です。それにもかかわらず、あっさりと終わりすぎてこれだけでは物足りないということもなく、単発でも観客に強い印象を残すマジックです。
この作品は現在でもプロアマ問わず、多くのマジシャンによって演じられています。しかし、この原案のハンドリングで演じている人は、あまり居ないようです。
当サイトでは古典作品を紹介する際には、できるだけ原案に近い手順を紹介しています。今回動画にした手順も、ドクター・デイリーのオリジナル手順を解説したと思われる「Dai Vernon’s Book of Magic」の記述に沿っています。
この原案を、現在一般的なハンドリングと比べた場合、優れている点もありますが、劣っている点もありそうに思います。
とくに、1枚目の黒いエースをテーブルに置く操作が、説得力十分とは言えないような感じもします。現代的な感覚では、テーブルに置く直前、パケット全体を裏返した後に、1度DL(技法名の略です)を入れたくなるところです。が、ここはぐっと堪えて、原案通りのハンドリングを踏襲してみました。
それから、2枚目のエースはパケット前方から縦に返す動きですが、これが自然なものであるかどうかも、若干の疑問はあります。石田隆信氏は、当時は縦に返すDLが多く使われていた影響もあるのではないか、との指摘をされています。
現代のこの奇術では、Bro. John HammanのGemini Countまたはそれに類するような動きで演じられることが多いです。この場合はパケットのボトムから横に向かってカードをめくり上げるような動作をします。
原案の構成であっても、パケット前方からではなくサイドからGemini Countのようにめくることは普通に可能です。原案ハンドリングに違和感を感じる場合は、この横からめくるハンドリングを取り入れてもいいかも知れません。
上記のような、ハンドリングの微細な違和感に対して、全体的に非常にシンプルに見える点は、逆にこの原案の優れた点でしょう。余計な並び替えの動作が無く、必要最小限と言えるハンドリングです。
前述の2枚目のエースの説得力が弱く思える、という点についても、余計な動きが無いという面から見ればむしろ利点とも思えます。
ドクター・デイリーのラストトリックはシンプルですが、これ単独で演じても十分に強い印象を残す効果的なマジックです。
しかし、場合によってはエースを使うほかのマジックと一緒に演じても良いと思います。例えば冒頭に挙げたツイスティング・ジ・エーセスとか、以前に紹介したOvertureとの組み合わせなども有りでしょう。
あるいは、最初にエースだけを使ってラストトリックを演じてから、他のカードも加えてエースアセンブリなどに続けても良いと思います。
ドクター・デイリーのラストトリックの演出について
このトリックは現象が1回だけの単純なものですが、その演出は様々なものが知られています。
上の動画で演じたのは、その中でも比較的単純な形でしょう。これは「Dai Vernon’s Book of Magic」でのオリジナル解説に沿ったものです。
現象だけを単純に見れば、黒いカードと赤いカードの交換現象です。しかし、このオリジナル演出をよく見ると、これが単なる交換現象として演じられているわけではないことに気づきます。
演出上の主題となっているのは、黒いカードのうちの1枚の位置を当てることです。つまり、これはモンテ現象としても見ることが出来ます。
ご存じない方のために補足すると、モンテとは、いくつかの候補の中に混ぜ込まれた特定の品物の位置を当てるという駆け引きを演じるものです。元々はマジックではなくイカサマ賭博の一種。スリーカードモンテとか、スリーシェルゲームなどが代表的な例です。
ラストトリックに話を戻すと、ここでは2枚の黒いカードを示し、どちらがスペードか?との質問を投げかける。そして結局は、選択の対象範囲外であったはずの、残りの2枚が黒いカードとなっている。
このパターンは、例えばUltimate Three Card Monteの最終段の構造とそっくりです。Three Card Monteの最も効果的なクライマックスだけを、単独で抜き出した現象と言えるかも知れません。それを思えば、これが観客に受けないはずはないですね。
いずれにしても、最初から交換現象であることを予感させず、あくまで2枚の中でスペードのAを当てるゲームだ、と観客に思わせる演出こそが、The Last Trick of Dr. Daleyの肝となる要素でしょう。
このモンテの要素を省いて、予定調和な交換現象として見せてしまうと、全く印象が変わってしまいます。つまり「おまじないをかけると、黒いエースと赤いエースが入れ替わってしまいます」みたいな直截的で意外性のない見せ方は、もはやデイリーのラストトリックとは違う別の何かだ、と言っても過言ではありません。
モンテとしての印象を強調するために、テーブル上に2枚の黒いエースを置いた後、位置を入れ替えて見せるのも良いかもしれません。実際に、一度のみならず数回の入れ替えを行って、わざとスペードの位置をわかりにくくさせたような演技をする人も居ます。
ただ、私の動画では2枚を重ねて置いて、そのままいっさい入れ替えたりしていません。これは原案の解説通りです。どちらが良いかは個人の好みに属することでしょうけども、私としては余計な入れ替えが無いほうがシンプルで良いかな、という感覚です。
同じモンテ演出の延長線上にある見せ方の中でも、マイケル・アマーが演じていたものは論理的で面白いと思いました。
氏の演技では、2枚の黒いエースを観客の手に置いた後、「スペードかクラブか、どちらのAが上にありますか?」と尋ねます。実際には、上は上でも、演者の持っているほうの上にある、という終わり方です。
ドクター・デイリーの原案では、意外性のあるオチではあるものの、特にそのことについて論理的な理由があるわけではありません。しかしアマーの見せ方では、演者のセリフには確かに嘘は無かったという、一貫した論理があります。
マジックは全部を論理で固める必要は無いと思いますが、こういう、後から考えてなるほどと納得できるようなセリフ回しは、観客の立場からはすっきりするかも知れませんね。
それ以外に、とくに日本でメジャーな演出として特筆すべきセリフは、「愛情とお金」というものです。前田知洋氏がテレビでよく演じられて広く知られていますので、むしろこの奇術自体の名前として「愛情とお金」と呼んでいる人も多いと思います。
原案ではテーブルに置くのは黒いエースですが、「愛情とお金」では赤いエースを置きます。ハートが愛情、ダイヤ(モンド)がお金を表すと説明し、観客に向かってどちらを選ぶかと尋ねるのです。そして、もしも欲張りにも両方を望んでしまうと、どちらも失ってしまうという皮肉なオチです。観客をマイナスの立場に置いたまま終わるという面はありますが、ジョークが利いていて面白い演出です。
ただ、この演出の考案者は分かっていないようです。
そのほかには、ビル・マローンの演出も面白いです。ここでは詳細の紹介は省きますが、当て物のモンテ現象ではなく、さりとて意外性の無い単なる交換現象でもない、盛り上がりのある見せ方で上手いと思いました。
ドクター・デイリーのラストトリックを解説した文献等
この奇術は元々、Lewis Ganson著「Dai Vernon’s Book of Magic」(1957)に収録されました。この本は、バーノンのカップ・アンド・ボールをはじめとして、古典として現代でも知られる作品を数多く解説した名著です。基本はバーノン作品集ですが、ジェイコブ・デイリーを始めとして、バーノンと親交のあった幾人かの奇術家による作品も含まれています。
オリジナルは古い本ですが、1994年にL&L Publishingから新装版として再版されています。またさらに同社から2011年に出された「Essential Dai Vernon」という、バーノン関連書籍の主要なものを合本にした本にも、「Dai Vernon’s Book of Magic」は含まれています。
日本語書籍では、東京堂出版の高木重朗著「カードマジック(奇術入門シリーズ)」に収録されています。この本では、「エースの入れかわり」と題して紹介されています。
この本で解説されているのは、原案のハンドリングです。
映像では、Michael Ammarの「Easy to Master Card Miracles Vol.2」、Darylの「Encyclopedia of Card Sleights Vol.7」、Bill Maloneの「On the Loose Vol.1」などに、それぞれ収録されています。これらはそれぞれ、原案とは異なる現代的なハンドリングです。

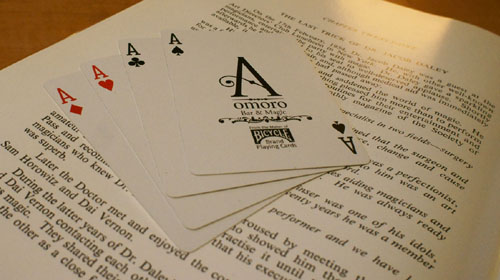









前田知洋さんの「愛情とお金」は、DVD「ナポリニコフの魔術学校」で見ることができます。ただ前田さんのハンドリングはデイリーと違いますね、演出の参考として観るには面白いです。
前田さんの演技は、知っているマジックでも何度も見たくなる良さがありますね。
ハンドリングは、一般的なGemini Countとも違う、また独特なやり方でしたね確か。氏の通常の手つきともマッチした感じでした。
ほかに氏の市販映像では、「スーパー クロースアップ マジック 前田知洋 奇跡の指先」にも収録されているみたいです。
何度見ても見飽きない手順ですよね。
クラシックの良さはどんな時代になっても錆びれない良さでしょうね。
ちょっと気付いたのですが…
使ってるカードが僕の良く行くマジックバーのオリジナルカードですね(笑)
オモロには行ったことあるんですか?
ありがとうございます。
私もそう若くないせいもあるのでしょうか、いや昔からですが、クラシックマジックが好みです。
A-Omoroには行ったことはありません。いつか行ってみたいんですけどね。
デックは、そこに出演されていたことのあるマジシャンから購入したものです。